選挙や政治、そして民主主義というゲームのルール自体をどう作り変えるか考えることだ。 (p.6).
日本では若者がマイノリティのため、投票率を高齢者並みに挙げても選挙結果は変わりません。
著者は現在の民主主義の問題点を明らかにして、再発明を主張しています。
人類は世の初めから気づいていた。人の能力や運や資源がおぞましく不平等なこと。そして厄介なことに、技術や知識や事業の革新局面においてこそ不平等が大活躍すること。したがって過激な不平等を否定するなら、それは進歩と繁栄を否定し、技術革新を否定する、仮想現実に等しいことを。 (p.31)
資本主義の格差に対し、勝利した大衆が立ち上げたのが民主主義です。水と油、ブレーキとアクセルの関係です。資本主義と民主主義はセットと思っていたためあまり意識していませんでしたが確かにそうだと思いました。
選挙という絆で結ばれた有権者と代議士・政治家の二人三脚は脆い。代議士や政治家は有権者に痛みを伴う即決即断や未来のための改革が苦手で、庶民の直感に反した専門家判断や技術的判断も敬遠しがちだからだ。 (p.62)
政治家がこれらを遠ざけるのは庶民から支持が得られないからです。庶民は未来より現在を求めるし、その求めに応じて未来への対策を怠ると問題が悪化します。
集めたデータから各論点・イシューについての意思決定を導き出すのは、自動化・機械化された意思決定アルゴリズムである。 ~意思決定アルゴリズムは不眠不休で働け、多数の論点・イシューを同時並行的に処理できる。人間が個々の論点について意識的に考えたり決めたりする必要が薄れる。「無意識」民主主義たるゆえんだ。 (p.139)
民主主義の構想です。アルゴリズムとは主にコンピューターで問題を解く方法、目標を達成する方法を示した手順や計算方法のことです。電車の乗換案内、カーナビ等に使われています。
無意識民主主義は一つの答えを与えてくれる。民意データを無意識に提供するマスの民意による意思決定(民主主義)、無意識民主主義アルゴリズムを設計する少数の専門家による意思決定(科学専制・貴族専制)、そして情報・データによる意思決定(客観的最適化)の融合が無意識民主主義であるからだ。(p.184-185)
民意データは選挙、街角の声を監視カメラ、マイクから拾うことで幅広いチャンネルから民意への解像度を高める、としています。
無意識民主主義は現在投票のみでしか表すことのできない民意データを抽出できます。しかしそれらは街角での監視カメラ、マイクからのデータ抽出となっていて庶民の理解は得られるか?という疑問があります。
この無意識民主主義を採用する国が出てくるのが22世紀になるか、早まるか、また採用されないかは分かりませんが、この構想は民意を広く汲み取るという長所はあると思いました。現在の感覚だとプライバシーの問題、意思決定アルゴリズムへの信頼度から実現不可能に思えますが将来はどうなるのでしょうか。
以上、「22世紀の民主主義」の書評でした。
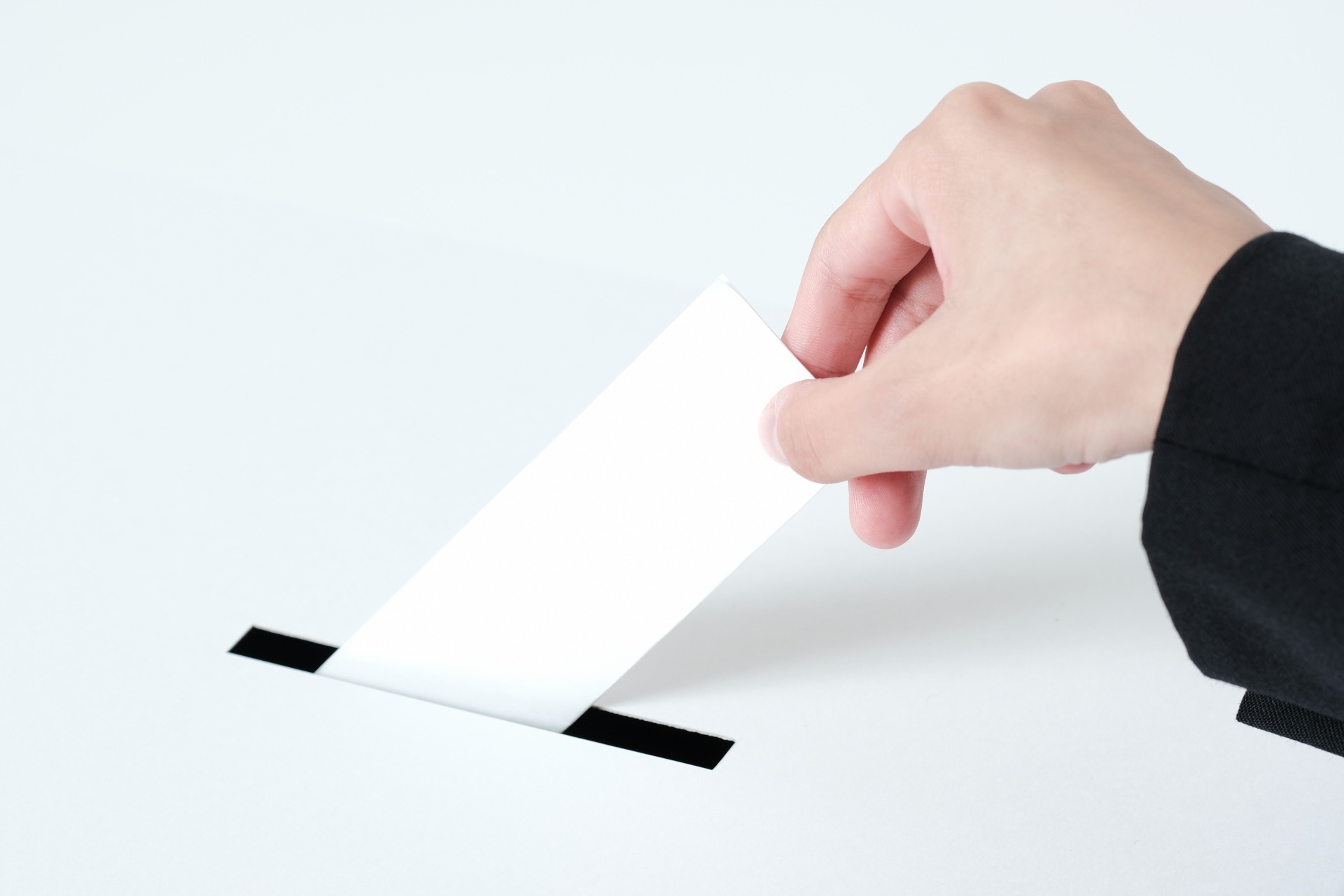


コメント