学問のすすめは言わずと知れた福沢諭吉の本ですが、それを「声に出して読みたい日本語」等で著名な齋藤孝さんが現代語に訳した本を読みました。「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」はあまりにも有名ですが、後半部分では齋藤さんも言われてるようにビジネス書的な要素があります。こちらに焦点をあててみました。
信じる、疑うということについては、取捨選択のための判断力が必要なのだ。
学問というのは、この判断力を確立するためにあるのではないだろうか。 p193
信じることには疑いが多く、疑うことには真理が多いとしています。
確かに個人的に自分が信じたこと以外に目を向けない傾向があると思いました。
目を向けないどころか疑うことすらしないかもしれません。
タイトルにある「学問」によってそうならないように判断力を身につけることができる、としています。
事業の成否・損得についてときどき自分の心の中でプラスマイナスの差し引き計算をしてみることである。商売で言えば棚卸しの決算のようなものだ。 p180
人生は、思いのほかに愚かなことをやり、事を成さないものである。この不都合をふせぐための手段として提言しています。事業だけでなく、自分自身の身の振り方についても「知性の徳と仕事の棚卸」によって今後の方針を立てられる、としています。
自分がどのような知識・経験を持ち、どんな性格かを把握することの重要さを説いていると解釈しました。
独立には2種類ある。一つは、形のあるもの。もう一つは、形のないものである。さらに分かりやすく言えば、品物についての独立と精神についての独立との2種類の区別である。 p204
品物についての独立は財産を持ち、自活するという意味で分かりやすいですが、精神についての独立は著者の言う通り奥が深いです。品物について独立していても他人と比べたり、金に支配されて精神の独立をしているか?としています。著者は金の使いすぎについて主に述べていますが逆に必要以上に金に縛られて必要なことにも金を惜しむのも精神の独立とは言えないと思いました。
このバランスをとることはなかなか難しいので自分なりの基準を持つ必要があります。
栄誉や人望を求めるべきなのだろうか。そのとおり。努力して求めるべきものである。ただこれを求めるにあたっては、相応のバランスをとることが重要なのだ。
人望は社会的な地位や財力で得られるものではなく、知性や人間性によるものなのは当然の道理だが、事実として反対の現象を見ることもある、としています。自分の働きを実際以下にしか見せられない人は自己アピールが必要であり、そのために何が必要かを具体的に挙げて説いています。
福沢が理想主義者ではなく現実主義者であることが分かります。
齋藤さんが解説しているようにこの本で勧める学問とは社会の役に立つ、実用的な学問です。
とりあげた14編から17編だけでも現在に通じる話がありました。タイトルに「学問」とあってアカデミックな、学者向けのものという勝手なイメージがありましたが、当時売れた理由が分かりました。
現代語によって身近なものとして読むことができました。文語体のままだったら読んでいないでしょう。
書かれたのが1872~1876年の明治初期ということで「日本は独立を保てるか?」という不安という当時の世相も垣間見えて興味深かったです。
以上、学問のすすめの書評でした。
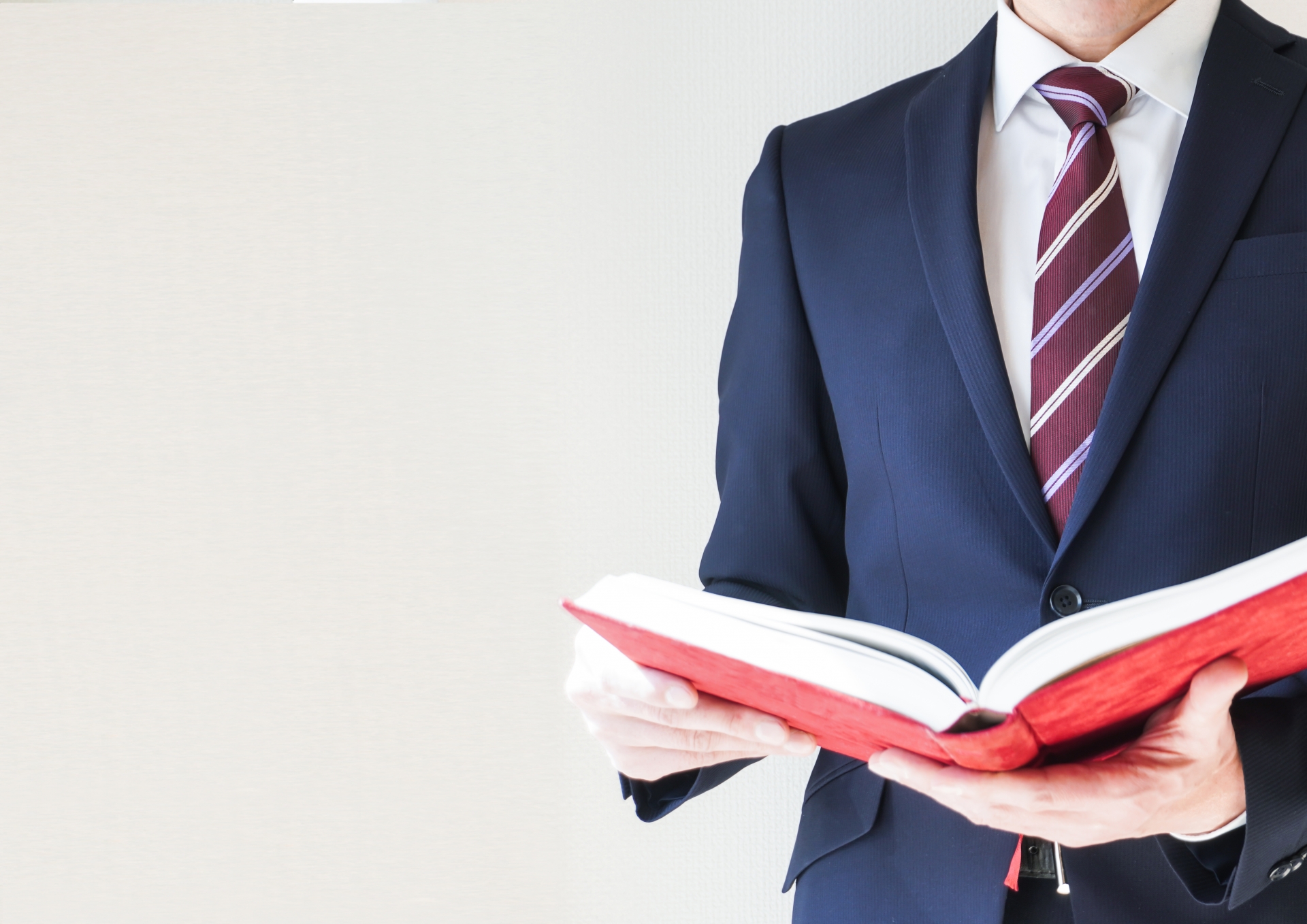


コメント